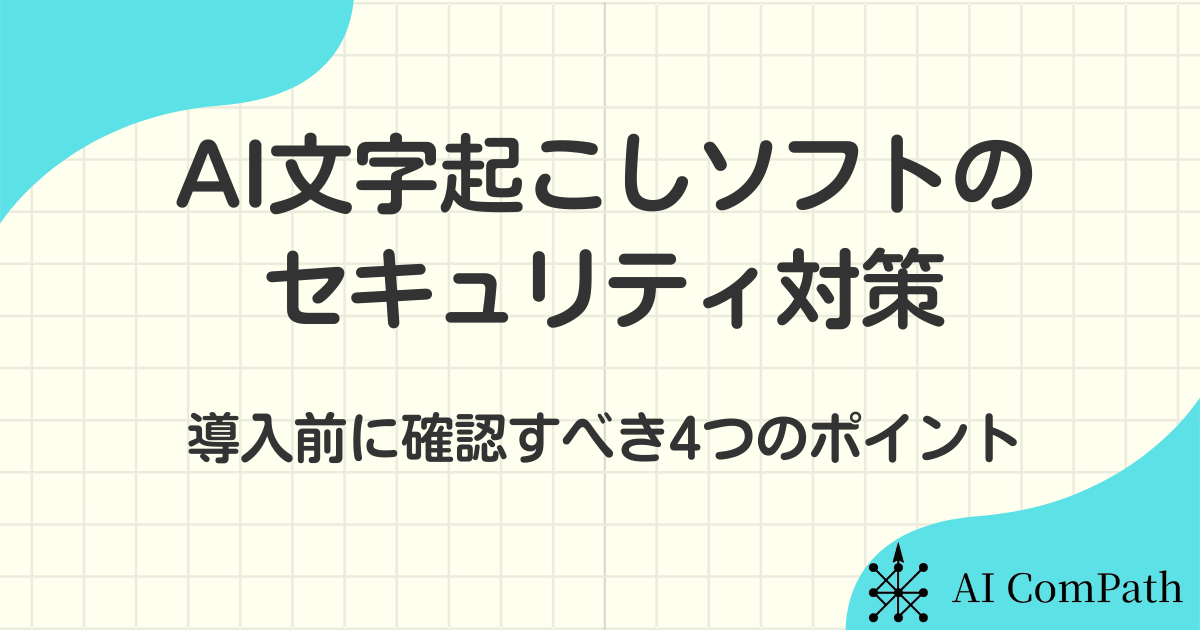AI文字起こしソフトは、会議の議事録作成やインタビュー整理を効率化できる便利なツールです。
しかし「機密情報を扱っても本当に安全なのか?」「会社に導入してセキュリティ審査を通せるのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際に、AI文字起こしソフトを導入する際は、クラウド型かローカル型かによってデータの扱いが異なり、暗号化や認証、ログ管理などセキュリティ機能の有無が重要になります。セキュリティチェックを怠ると、思わぬリスクにつながる可能性もあります。
そこで本記事では、AI文字起こしソフトのセキュリティ面を確認するポイントをわかりやすく整理しました。さらに、セキュリティ対策が充実しているおすすめツールも紹介します。
「安心して使えるAI文字起こしソフトを導入したい」「上司や情報システム部門に提案する前にリスクを把握したい」という方は、ぜひ参考にしてください。
AI文字起こしソフトのセキュリティって大丈夫?
AI文字起こしソフトは便利な一方で、「機密情報を扱って大丈夫なのか?」 という不安を抱く方も少なくありません。特に会社で導入する場合、社内規程や情報システム部門からセキュリティチェックを求められることが一般的です。
クラウド型とローカル型の違い
AI文字起こしソフトは大きく クラウド型 と ローカル型 に分けられます。
| 種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| クラウド型 | データをインターネット経由で送信し、サーバー側で処理 | PCやスマホから手軽に利用可能、機能更新が早い | データが外部に送信されるため、保存方針や暗号化の有無を確認する必要がある |
| ローカル型 | デバイスや専用機器で処理 | データが外に出にくく、機密情報を扱いやすい | 専用機器の導入が必要、クラウド連携が少ないケースもある |
クラウド型は利便性が高く、ほとんどの人気サービスがこの方式を採用しています。一方で、データの取り扱いルールが明確に示されているかどうかを確認する必要があります。
想定されるセキュリティリスク
AI文字起こしソフトを利用する際に考えられる主なリスクは以下の通りです。
- データ漏洩 → 録音データや文字起こし結果が外部に流出するリスク
- 不正アクセス → 第三者がアカウントに侵入し、会議データを閲覧するリスク
- 誤利用 → 社内の利用者が誤ってデータを共有・公開してしまうリスク
- 保存期間の不透明さ → どのくらいサーバーにデータが残るのか不明確な場合
こうしたリスクは、提供会社のセキュリティ体制や搭載されている機能によって軽減できます。実際に導入を検討する際は、暗号化や認証機能、監査ログの有無などを確認することが不可欠です。
安心して利用するために確認しておきたい機能4つ
AI文字起こしソフトを導入する際には、便利さだけでなく 「セキュリティ要件を満たせるか」 をチェックする必要があります。特に法人利用では、以下の4点が揃っているかを必ず確認することをおすすめします。
ユーザー認証機能
利用者が正しく認証される仕組みは基本中の基本です。
- 二段階認証(2FA)
- シングルサインオン(SSO)
- アカウント権限管理(管理者・利用者の区分け)
これらが備わっていれば、不正ログインや第三者による情報閲覧リスクを大幅に下げられます。
・2FA(二段階認証)
IDとパスワードに加え、SMSコードやアプリ通知などを使ってログインする方法。不正ログインを防ぐための仕組みです。
・SSO(Single Sign-On)
一度ログインすれば、複数のサービスを再ログインなしで使える仕組み。利便性と安全性の両方に役立ちます。
データの暗号化機能
録音データや文字起こし結果は、多くの場合クラウドサーバーで処理されます。その際に重要なのが暗号化です。
- 通信時の暗号化(TLS/SSL)
- 保存時の暗号化(AESなど)
さらに、データ保持期間や削除ポリシーが明示されているかも確認しましょう。
・TLS(Transport Layer Security)
インターネット上でデータを送るときに盗み見や改ざんを防ぐ仕組み。銀行サイトやログイン画面でも使われています。
・AES(Advanced Encryption Standard)
データを保存するときに強力に暗号化する技術。世界的に標準となっており、解読がほぼ不可能とされます。
監査ログ / 追跡機能
「誰がいつ、どのデータにアクセスしたか」が記録される監査ログは、企業利用に必須の機能です。
- 情報漏洩や不正利用が起きた場合の追跡が可能
- 利用者の操作履歴を残せるので、内部統制にも役立つ
社内コンプライアンスやセキュリティ監査で確認されるポイントでもあります。
文字起こしソフト提供会社のセキュリティ体制
最後に重要なのは、提供会社そのものの信頼性です。
- ISO/IEC 27001(ISMS) などの国際的な認証取得
- GDPRやCCPAへの対応状況
- 国内外の企業導入実績
これらが明記されているかどうかで、安心感が大きく変わります。特に会社で導入を検討する際は「どの認証を持っているか」を上申資料に記載できると、安心材料を与えることができるでしょう。
・ISO27001(ISMS認証)
情報セキュリティ管理の国際規格。企業がデータを安全に扱う体制を整えていることを第三者が認めた証明です。
・GDPR(General Data Protection Regulation)
EUで定められた個人情報保護の法律。ユーザーの同意なしにデータを使えないなど、非常に厳しいルールです。
・CCPA(California Consumer Privacy Act)
アメリカ・カリフォルニア州の個人情報保護法。ユーザーは自分のデータ利用について「知る権利」「拒否する権利」などを持ちます。
セキュリティに配慮したAI文字起こしソフト3選
セキュリティ要件を満たしつつ、日常業務でも安心して利用できるAI文字起こしソフトを3つ紹介します。公式に明示されている機能や料金をもとに比較しました。
Notta
Nottaは世界的に利用されているクラウド型の文字起こしサービスです。58言語対応で、翻訳は42言語に対応。無料プランでは月120分まで文字起こし可能で、手軽に試せます。ビジネスプランに切り替えれば、利用時間や機能が大幅に拡張されます。
特に強みはセキュリティ体制です。ISO27001やSOC2 Type II認証を取得しており、通信はTLS1.2、保存はAES-256で暗号化されています。さらにGDPR・CCPA・HIPAA準拠を掲げており、海外企業とのやり取りにも安心です。
AutoMemo
AutoMemoはソースネクストが提供するアプリ型の文字起こしサービスです。料金は年額15,360円(1,280円/月)〜で、無料でも月1時間の文字起こし+要約1回を試せます。有料プランでは月30時間まで利用可能で、会議や取材にも十分対応します。
対応言語は72言語で、多言語の文字起こしに強いのが特徴です。また話者ごとの分離機能に対応しているため、会議で複数人が発言する場面でも使いやすいです。ただし、セキュリティ体制に関する詳細(暗号化や認証取得など)は公式サイトには明記されていません。導入を検討する場合は事前に確認することをおすすめします。
WITH TEAM
WITH TEAMは、法人向けのBPO型文字起こしサービスです。料金は1文字0.5円〜で、利用量に応じて見積もりされます。無料トライアルはなく、時間制限についても公式には記載されていません。
企業向けに提供されているサービスであるため、精度や運用面の安心感は期待できますが、セキュリティ体制や機能の詳細は公式サイトに明示されていないため、導入時には直接問い合わせる必要があります。
| ツール名 | 料金 | 無料お試し | 文字起こし時間 | 多言語対応 | カスタム辞書 | 話者識別 | セキュリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notta | Free 0円Pro:1,317円/月Business:2,508円/月 | 月120分まで無料(1会話3分) | 120分/月(無料枠)、有料は拡張可 | 58言語(翻訳42言語) | あり(英語・日本語) | あり | ISO27001 / SOC2取得、TLS・AES暗号化、GDPR/CCPA/HIPAA準拠 |
| AutoMemo | 年額15,360円(1,280円/月)〜 | 無料:文字起こし1時間/月+要約1回 | Premium:30時間/月(上位プランあり) | 72言語(翻訳明記なし) | 記載なし | あり(話者ごと分離) | 公式に明記なし(要確認) |
| WITH TEAM | 1文字0.5円〜(利用量で見積) | なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 公式にセキュリティ情報なし(要問い合わせ) |
このように比較すると、セキュリティ要件が明確に示されているのはNottaであり、社内導入の審査を通しやすい特徴があります。AutoMemoは多言語対応や話者識別に強みがありますが、セキュリティ面は追加確認が必要です。WITH TEAMは法人向けですが、詳細が非公開のため、導入検討時には問い合わせが前提となります。
まとめ
AI文字起こしソフトは業務効率を大きく向上させますが、セキュリティ確認は必須です。特に会社で導入する場合は、ユーザー認証・データ暗号化・監査ログ・提供会社のセキュリティ体制といったポイントを事前にチェックしておくことで、安心して利用できます。
本記事で紹介した3つのサービスを比較すると、
- Notta はセキュリティ認証が明確で、導入審査に通しやすい
- AutoMemo は多言語や話者識別に強いが、セキュリティ情報は要確認
- WITH TEAM は法人向けに柔軟だが、詳細は問い合わせ前提
といった特徴があります。
まずは自社のセキュリティ規程や利用目的に照らして、どのツールが最適かを判断することが重要です。安心できるサービスを選ぶことで、効率化と情報保護の両立が可能になります。